01.はじめに
Excelでデータ分析や集計を行う際、SUM関数は必須の関数です。この関数を使いこなせれば、大量のデータも瞬時に合計でき、業務効率が格段に向上します。
この記事では、SUM関数の基本的な使い方から、様々な場面での活用方法、エラーへの対処法、そして他の関数との組み合わせ技まで、初心者にも分かりやすく徹底解説します。
オートSUM機能やSUMIF、SUMIFS、COUNTIF関数との連携など、実践的なテクニックも紹介。この記事を読み終える頃には、あなたはSUM関数のエキスパートになっているはずです。
- 01.はじめに
- 02.SUM関数の基本
- 03.SUM関数を使った様々な合計計算
- 04.SUM関数とオートSUM機能
- 05.SUM関数で発生するエラーと対処法
- 06.SUM関数と他の関数との組み合わせ技
- 07.Excel SUM関数 実践練習問題
- 08.まとめ
02.SUM関数の基本
SUM関数は、Excelにおいて最も基本的な関数のひとつであり、指定した数値やセルの合計を計算するために使用されます。
計算式を自分で入力する手間を省き、迅速かつ正確に合計値を求めることができます。
表計算ソフトを使う上で必須とも言えるでしょう。関数の中でも使用頻度が高い関数です。日々の業務や家計簿の作成など、様々な場面で活用できます。
SUM関数の構文
SUM関数の基本的な構文は以下のとおりです。
=SUM(数値1, [数値2], ...)
または
=SUM(セル範囲1, [セル範囲2], ...)
| 引数 | 説明 |
|---|---|
| 数値1, 数値2,… | 合計したい数値を直接入力します。カンマで区切って複数の数値を指定できます。 |
| セル範囲1, セル範囲2,… | 合計したい数値が入力されているセル範囲を指定します。こちらもカンマで区切って複数のセル範囲を指定できます。セル範囲の指定方法は、例えばA1からA10までの範囲であれば「A1:A10」と記述します。 |
引数は最大255個まで指定できます。 数値とセル範囲を混在させて指定することも可能です。
SUM関数の使い方
具体的なSUM関数の使い方を例を挙げて説明します。
数値の直接入力
例えば、10、20、30という3つの数値の合計を求めたい場合は、以下の式を入力します。
=SUM(10, 20, 30)
この式を入力すると、セルには60という合計値が表示されます。
セル範囲の指定
A1セルに10、A2セルに20、A3セルに30という数値が入力されている場合、これらのセルの合計を求めるには、以下の式を入力します。
=SUM(A1:A3)
または
=SUM(A1,A2,A3)
この式を入力すると、セルには60という合計値が表示されます。セル範囲を指定する場合、「:」(コロン)を使うことで連続したセル範囲を、「,」(カンマ)を使うことで離れたセルを指定できます。
空白セルや文字列が入力されているセルは、SUM関数では0として扱われます。 エラー値が含まれている場合は、エラー値が返されます。
例えば、#VALUE!エラーが含まれるセル範囲を指定すると、SUM関数も#VALUE!エラーを返します。
03.SUM関数を使った様々な合計計算
SUM関数は、Excelで最も基本的な関数の1つであり、様々な方法で合計計算を行うことができます。
ここでは、数値、セル、範囲、複数の範囲といった様々なケースでの合計計算方法を具体例と共に解説します。
これらの例を通して、SUM関数の柔軟性と活用の幅広さを理解しましょう。
数値の合計
SUM関数を使って、直接数値を合計することができます。例えば、10、20、30を合計したい場合は、以下のように入力します。
=SUM(10, 20, 30)
この場合、結果は60となります。カンマで区切ることで、複数の数値を指定できます。
セルの合計
特定のセルに入力されている数値を合計することも可能です。例えば、A1セル、B1セル、C1セルに入力されている数値を合計したい場合は、以下のように入力します。
=SUM(A1, B1, C1)
各セルをカンマで区切って指定することで、セルに入力されている値が合計されます。セル参照を用いることで、セル内の値が変更された場合でも、自動的に合計値が更新されるため、非常に便利です。
範囲の合計
連続したセル範囲の合計を計算する場合は、コロン(:)を使って範囲を指定します。例えば、A1セルからA10セルまでの数値を合計したい場合は、以下のように入力します。
=SUM(A1:A10)
この方法を使うと、大量のデータの合計を簡単に計算できます。 また、行だけでなく列の範囲指定も可能です(例:A1:C1)。
複数の範囲の合計
SUM関数は、複数の範囲を同時に指定して合計することも可能です。例えば、A1セルからA10セルまでと、C1セルからC10セルまでの数値を合計したい場合は、以下のように入力します。
=SUM(A1:A10, C1:C10)
カンマで区切ることで、複数の範囲を指定できます。離れた場所にあるデータの合計を計算する際に役立ちます。
| 計算方法 | 入力例 | 説明 |
|---|---|---|
| 数値の合計 | =SUM(10, 20, 30) |
直接数値を指定して合計を計算 |
| セルの合計 | =SUM(A1, B1, C1) |
特定のセルを指定して合計を計算 |
| 範囲の合計 | =SUM(A1:A10) |
連続したセル範囲を指定して合計を計算 |
| 複数の範囲の合計 | =SUM(A1:A10, C1:C10) |
複数のセル範囲を指定して合計を計算 |
上記のように、SUM関数は様々な方法で合計計算を行うことができます。状況に応じて適切な方法を選択することで、効率的にデータの集計を行うことができます。
これらの基本的な使い方をマスターすることで、Excelでのデータ分析がよりスムーズになります。
04.SUM関数とオートSUM機能
SUM関数はExcelで合計を求めるための基本的な関数ですが、より手軽に合計を計算する方法としてオートSUM機能があります。
オートSUM機能は、選択したセル範囲の合計を自動的に計算し、SUM関数を入力してくれる便利な機能です。キーボードのショートカットやリボンから簡単にアクセスできるため、日常的にExcelを使う上で必須の機能と言えるでしょう。
オートSUM機能の使い方
オートSUM機能を使う方法はいくつかあります。代表的な方法を3つ紹介します。
-
リボンから利用する:「ホーム」タブの「編集」グループにある「オートSUM」ボタンをクリックします。選択したセル範囲の合計が自動的に計算され、SUM関数が該当セルに入力されます。
データを入力したセル範囲の隣接する空のセルを選択してからオートSUMボタンをクリックすると、Excelが自動的に合計範囲を予測し、SUM関数を挿入してくれます。 -
キーボードショートカットを利用する:合計を計算したいセルを選択し、
Alt+=キーを押すと、Excelが自動的に合計範囲を予測し、SUM関数を挿入します。その後、Enterキーを押すことで合計値が計算されます。 -
数式バーから利用する:合計を計算したいセルを選択し、数式バーに「=SUM(」と入力します。その後、合計したいセル範囲をドラッグで選択するか、キーボードで入力し、閉じ括弧「)」を入力して
Enterキーを押します。
オートSUM機能のメリット
オートSUM機能には、SUM関数を手動で入力するよりも多くのメリットがあります。
| メリット | 説明 |
|---|---|
| 時間の節約 | SUM関数の構文を手入力する必要がなく、数クリックまたはショートカットキーで合計を計算できるため、作業時間を大幅に短縮できます。特に大量のデータを取り扱う場合、その効果は絶大です。 |
| 入力ミスの軽減 | 関数の入力ミスやセル範囲の指定ミスを減らすことができます。手入力によるタイプミスや、セル範囲の選択ミスによる計算エラーのリスクを軽減し、正確な計算結果を得ることができます。 |
| 操作の簡便化 | Excel初心者でも簡単に合計計算を行うことができます。直感的な操作で合計を計算できるため、Excelの操作に慣れていない人でも容易に利用できます。 |
| 作業効率の向上 | 上記のメリットにより、作業効率が向上します。迅速かつ正確に合計を計算できるため、他の作業に時間を割くことができ、全体の作業効率を向上させることができます。 |
オートSUM機能は、大量のデータの集計や、頻繁に合計計算を行う必要がある場合に特に役立ちます。例えば、売上データの集計、家計簿の作成、学生の成績管理など、様々な場面で活用できます。
SUM関数と合わせてオートSUM機能を使いこなすことで、Excelでの作業効率を格段に向上させることができるでしょう。
05.SUM関数で発生するエラーと対処法
SUM関数は非常に便利ですが、使い方を誤るとエラーが発生することがあります。エラーの種類を理解し、適切な対処法を学ぶことで、スムーズなデータ分析が可能になります。ここでは、SUM関数でよく発生するエラーと、その対処法について詳しく解説します。
#VALUE!エラー
#VALUE!エラーは、SUM関数の引数に数値以外の値(文字列、日付など)が含まれている場合に発生します。
例えば、セルA1に”りんご”、セルA2に10という値が入力されている状態で、=SUM(A1:A2)とすると、#VALUE!エラーが表示されます。これは、”りんご”という文字列を数値として計算できないことが原因です。
#VALUE!エラーの対処法
#VALUE!エラーを解決するには、以下の方法があります。
- 数値以外の値が含まれているセルを修正する: セル内の文字列を削除するか、数値に変換します。
- SUM関数ではなく、SUMIF関数を使用する: SUMIF関数を使用することで、特定の条件を満たす数値のみを合計することができます。
例えば、数値以外の値を除外して合計したい場合は、ISNUMBER関数と組み合わせて使用します。=SUMIF(A1:A2,ISNUMBER(A1:A2)) - エラーを無視して数値のみ合計する: AGGREGATE関数を使用することで、エラー値を無視して数値のみを合計することができます。
=AGGREGATE(9,6,A1:A2) は、A1:A2の範囲内でエラー値を無視し、合計値を返します。9はSUM、6はエラー値を無視するオプションです。
#REF!エラー
#REF!エラーは、SUM関数が参照しているセルが無効になっている場合に発生します。例えば、SUM関数が参照しているセルが削除されたり、シートが削除されたりした場合に発生します。
#REF!エラーの対処法
#REF!エラーを解決するには、以下の方法があります。
- 削除されたセルまたはシートを復元する:「元に戻す」機能を使用して、削除されたセルまたはシートを復元します。
- SUM関数の参照先を修正する: SUM関数の引数を修正し、有効なセルまたは範囲を参照するようにします。
- INDIRECT関数を使用する: INDIRECT関数を使用することで、文字列で指定したセル範囲を参照することができます。これにより、セルやシートが移動または削除された場合でも、参照先を動的に変更することができます。
- 例えば、”Sheet1!A1:A10″という文字列で指定されたセル範囲を合計したい場合は、=SUM(INDIRECT(“Sheet1!A1:A10”))とします。
#NAME?エラー
#NAME?エラーは、SUM関数の名前が正しく入力されていない場合に発生します。例えば、SUM関数を”SM”と誤入力した場合などに発生します。
#NAME?エラーの対処法
#NAME?エラーを解決するには、以下の方法があります。
- 関数名を修正する: 関数名が正しく入力されているか確認し、必要に応じて修正します。Excelのオートコンプリート機能を利用すると、関数名を正確に入力することができます。
- 定義名を確認する: 定義名を使用している場合は、定義名が正しく定義されているか確認します。定義名が正しく定義されていない場合は、定義名を修正するか、定義名を削除します。
| エラーの種類 | 原因 | 対処法 |
|---|---|---|
| #VALUE! | 数値以外の値が引数に含まれている | 数値以外の値を修正、SUMIF関数を使用、AGGREGATE関数を使用 |
| #REF! | 参照しているセルが無効 | 削除したセル/シートを復元、SUM関数の参照先を修正、INDIRECT関数を使用 |
| #NAME? | 関数名が正しくない | 関数名を修正、定義名を確認 |
これらのエラーへの対処法を理解することで、SUM関数をより効果的に活用し、正確なデータ分析を行うことができます。エラーが発生した場合は、慌てずに上記の方法を試してみてください。
06.SUM関数と他の関数との組み合わせ技
SUM関数は単体でも強力な関数ですが、他の関数と組み合わせることで、より複雑な条件下での合計計算が可能になります。ここでは、SUM関数と相性の良い関数をいくつか紹介します。
SUMIF関数と組み合わせる
SUMIF関数は、指定した条件に一致するセルのみの合計を求める関数です。特定の条件を満たすデータのみを合計したい場合に非常に便利です。
例えば、売上データから特定の商品のみの売上合計を求めたい場合、SUMIF関数と組み合わせることで簡単に計算できます。
| 関数 | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| SUMIF | 指定した条件に一致するセルの合計を求める | =SUMIF(A1:A10,”りんご”,B1:B10) (A1:A10の範囲で「りんご」という文字列と一致するセルの隣の列B1:B10の値を合計) |
SUMIF関数の使用例
商品の種類がA列に、売上金額がB列に記載されているとします。この時、「りんご」の売上合計を求めるには、以下の式を使用します。
=SUMIF(A1:A10,"りんご",B1:B10)
SUMIFS関数と組み合わせる
SUMIFS関数は、複数の条件に一致するセルのみの合計を求める関数です。SUMIF関数が一つの条件しか指定できないのに対し、SUMIFS関数は複数の条件を指定できます。
例えば、売上データから特定の地域、特定の商品の売上合計を求めたい場合、SUMIFS関数を使用します。
| 関数 | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| SUMIFS | 複数の指定した条件に一致するセルの合計を求める | =SUMIFS(C1:C10,A1:A10,”りんご”,B1:B10,”東京”) (C1:C10の合計を、A1:A10が「りんご」、B1:B10が「東京」という条件で求める) |
SUMIFS関数の使用例
商品の種類がA列に、販売地域がB列に、売上金額がC列に記載されているとします。この時、「東京」で販売された「りんご」の売上合計を求めるには、以下の式を使用します。
=SUMIFS(C1:C10,A1:A10,"りんご",B1:B10,"東京")
COUNTIF関数と組み合わせる
COUNTIF関数は、指定した条件に一致するセルの個数を数える関数です。SUM関数と直接組み合わせるわけではありませんが、特定の条件を満たすデータの個数に基づいて合計を計算する場合に役立ちます。
| 関数 | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| COUNTIF | 指定した条件に一致するセルの個数を数える | =COUNTIF(A1:A10,”りんご”) (A1:A10の範囲で「りんご」という文字列と一致するセルの個数を数える) |
COUNTIF関数とSUM関数の組み合わせ使用例
商品の種類がA列に記載され、各商品が一つにつき100円の売上だとします。A列に「りんご」がいくつあるか数え、その数に100円を掛けて「りんご」の売上合計を求めるには、以下の式を使用します。
=COUNTIF(A1:A10,"りんご")*100
このように、SUM関数と他の関数を組み合わせることで、様々な条件下での合計計算を効率的に行うことができます。それぞれの関数の特性を理解し、適切に使い分けることで、Excelのデータ分析能力を最大限に活用しましょう。
07.Excel SUM関数 実践練習問題
SUM関数を実際に使ってみましょう!以下の練習問題を通して、より理解を深めてください。
問題1:基本的な合計計算
以下の表は、A社の各支店の売上高です。SUM関数を使って、全支店の売上高の合計を求めてください。
| 支店 | 売上高(万円) |
|---|---|
| 東京 | 120 |
| 大阪 | 150 |
| 名古屋 | 80 |
| 福岡 | 100 |
解答:=SUM(B2:B5) 合計:450万円
問題2:特定のセルの合計
以下の表は、B社の商品別売上高です。商品Aと商品Cの売上高の合計を求めてください。
| 商品 | 売上高(万円) |
|---|---|
| 商品A | 50 |
| 商品B | 70 |
| 商品C | 60 |
| 商品D | 90 |
解答:=SUM(B2,B4) 合計:110万円
問題3:複数の範囲の合計
以下の表は、C社の部署別経費です。営業部と開発部の経費の合計を求めてください。
| 部署 | 経費(万円) |
|---|---|
| 営業部 | 30 |
| 企画部 | 20 |
| 開発部 | 40 |
| 管理部 | 10 |
解答:=SUM(B2,B4) 合計:70万円
問題4:空白セルを含む合計
以下の表は、D社の社員の残業時間です。空白セルがあっても正しく合計を求めてください。
| 社員 | 残業時間(時間) |
|---|---|
| 佐藤 | 10 |
| 田中 | |
| 鈴木 | 5 |
| 加藤 | 15 |
解答:=SUM(B2:B5) 合計:30時間 (空白セルは0として扱われます)
問題5:数値と数値の文字列が混在する合計
以下の表は、E社の商品の在庫数です。数値と数値の文字列が混在していますが、正しく合計を求めてください。
| 商品 | 在庫数 |
|---|---|
| 商品A | 10 |
| 商品B | “5” |
| 商品C | 20 |
解答:=SUM(B2:B4) 合計:35個 (数値の文字列も数値として扱われます)
これらの練習問題を通して、SUM関数の様々な使い方を理解していただけたでしょうか。SUM関数はExcelの基本的な関数ですが、非常に多くの場面で活用できます。ぜひ、実務でも活用してみてください。
08.まとめ
この記事では、ExcelのSUM関数について、基本的な使い方から応用までを解説しました。SUM関数は、数値やセル、範囲の合計を計算する際に非常に便利な関数です。
オートSUM機能を使えば、より簡単に合計を計算できます。SUMIF関数やSUMIFS関数、COUNTIF関数と組み合わせることで、より複雑な条件での合計計算も可能です。
エラーが発生した場合の対処法も理解しておくと、スムーズに作業を進められます。実践練習問題を通して、学んだ知識を実際に試してみてください。
この記事が、Excelでのデータ分析や集計作業の効率化に役立つことを願っています。

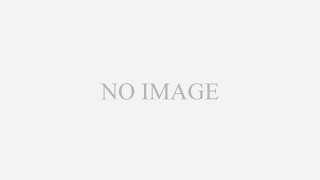
コメント