- 01. 「SUMIF」とは?単一条件での合計が簡単に
- 02. 「SUMIFS」で複数条件を自在に扱う
- 03. 「COUNTIF」で条件に合う件数を数える
- 04. 「COUNTIFS」で複数条件の件数をカウント
- 05. これも覚えておきたい!似た状況で便利な関数たち
- 06. 関数を「使いこなす」コツと練習方法
01. 「SUMIF」とは?単一条件での合計が簡単に
「SUMIF」の基本構文と意味
エクセル関数「SUMIF」は、ある条件に合致するデータだけを対象に、その合計を計算してくれる関数です。 つまり「条件を満たすものだけを足したい」というときに使います。
基本構文は以下のとおりです。
=SUMIF(範囲, 条件, 合計範囲)
- 範囲:条件をチェックするセル範囲
- 条件:どのデータを対象にするかの条件(例:”東京”, “>=100” など)
- 合計範囲:合計を求めたい数値が入っている範囲
よくある使用シーンと例
例えば、売上データの表があり、「担当者が佐藤の売上合計を出したい」といったケースで使います。
=SUMIF(A2:A10, "佐藤", C2:C10)
この例では、A列が担当者名、C列が売上金額です。
「A列で佐藤と一致する行のC列の数値」を合計してくれます。
トラブルシューティング:「範囲」と「合計範囲」がズレてる?
初心者がよくつまずくポイントが、「範囲」と「合計範囲」の行数が一致していないケースです。 たとえば、範囲がA2:A10なのに、合計範囲がC2:C9のように1行少ないと、意図しない結果になります。
関数は「1行目は1行目同士、2行目は2行目同士」を照合しているため、ズレていると正しく計算できません。
関数がうまく動かないときは、まず範囲のサイズが一致しているかを確認しましょう。
02. 「SUMIFS」で複数条件を自在に扱う
「SUMIFS」の構文と違いを理解する
「SUMIFS」は、「SUMIF」の拡張版で、複数の条件を指定して合計を求める関数です。 「部署が営業部」で「日付が2024年4月」のように、AND条件で絞り込みたいときに使います。
基本構文は以下のとおりです。
=SUMIFS(合計範囲, 条件範囲1, 条件1, 条件範囲2, 条件2, ...)
- 合計範囲:合計したい値が入っているセル範囲
- 条件範囲:条件を当てはめる対象の範囲(複数指定可能)
- 条件:各条件範囲に対する条件
2条件・3条件での使用例(部署×日付など)
以下のような売上データを例に考えます。
- A列:日付
- B列:部署
- C列:売上金額
「2024年4月」に「営業部」で発生した売上合計を出すには、以下のように記述します。
=SUMIFS(C2:C100, A2:A100, ">=2024/4/1", A2:A100, "<=2024/4/30", B2:B100, "営業部")
日付の範囲と部署の条件を同時に指定して、合計を出しています。 複数条件でも、順番に「範囲」「条件」「範囲」「条件」と書いていくだけでOKです。
AND条件の組み合わせ例
「Aさん」が「営業部」で出した売上を知りたいときも、「SUMIFS」で対応できます。
=SUMIFS(C2:C100, B2:B100, "営業部", D2:D100, "Aさん")
このように「複数の条件をすべて満たす場合のみ合計」したいときに、SUMIFSは非常に便利です。
なお、「OR条件(どちらかを満たす)」には対応していないため、工夫が必要になります(これについては後述のSUMPRODUCTで扱います)。
03. 「COUNTIF」で条件に合う件数を数える
「COUNTIF」の構文と使い方
「COUNTIF」は、指定した条件に合うセルの数をカウントする関数です。 たとえば「A列に“佐藤”と書かれたセルが何個あるか」を数えたいときに使います。
基本構文はこちらです。
=COUNTIF(範囲, 条件)
- 範囲:条件をチェックするセル範囲
- 条件:一致させたい値や数式(例:”佐藤”, “>100” など)
具体例:ある商品が売れた回数を数える
以下のような販売データがあったとします。
- A列:日付
- B列:商品名
「B列で“りんご”という商品が売れた回数」を知りたい場合、次のように記述します。
=COUNTIF(B2:B100, "りんご")
これで、B列に「りんご」と記載されたセルの数を自動的にカウントできます。
部分一致・ワイルドカードの使い方も便利
COUNTIFでは、文字列の一部だけが一致する場合や、「前方一致」「後方一致」を調べたいときにワイルドカード(* や ?)が使えます。
例えば、「佐藤」で始まる名前(例:「佐藤一郎」「佐藤美咲」)を数えたいときは、
=COUNTIF(A2:A100, "佐藤*")
逆に、「~美咲」という名前で終わるものを数えたいときは、
=COUNTIF(A2:A100, "*美咲")
となります。
ワイルドカードを上手に使うことで、柔軟なカウントが可能になります。
04. 「COUNTIFS」で複数条件の件数をカウント
「COUNTIFS」の構文と実例
「COUNTIFS」は、「COUNTIF」の複数条件版です。 たとえば「担当者が佐藤」で「部署が営業部」のように、複数の条件に合うデータの件数をカウントしたいときに使います。
基本構文は以下のとおりです。
=COUNTIFS(条件範囲1, 条件1, 条件範囲2, 条件2, ...)
- 条件範囲:条件を適用する範囲
- 条件:各条件範囲に対する条件
COUNTIFSでは、「すべての条件を満たす行」がカウントされます。 AND条件による絞り込みとして非常に有効です。
2つ以上の条件でフィルタリングカウント
例えば、以下のようなデータがあるとします。
- A列:日付
- B列:担当者
- C列:部署
「2024年4月中に、営業部の佐藤さんが関わった件数」を知りたい場合は、次のように書きます。
=COUNTIFS(A2:A100, ">=2024/4/1", A2:A100, "<=2024/4/30", C2:C100, "営業部", B2:B100, "佐藤")
このように、複数の条件を掛け合わせてピンポイントのデータ件数を取得できます。
文字列や日付にも対応できるのか?
COUNTIFSは、文字列・数値・日付などあらゆるデータ形式に対応しています。 ただし、日付を直接セルに書く場合は「”2024/4/1″」のように文字列形式で指定する必要があります。
また、文字列に関しては「完全一致」が基本ですが、前章の「COUNTIF」と同様にワイルドカード(*や?)を使えば部分一致検索も可能です。
=COUNTIFS(B2:B100, "佐藤*", C2:C100, "営業部")
このように柔軟な条件設定ができるのも、COUNTIFSの大きな魅力です。
05. これも覚えておきたい!似た状況で便利な関数たち
「SUMPRODUCT」で複雑な条件でも合計可能
「SUMPRODUCT」は、複数の条件を使った集計やカウントに強い関数です。 一見難しそうに見えますが、SUMIFSでは表現しきれない複雑な条件や、OR条件の合計などを可能にします。
例えば、「営業部」または「販売部」の売上合計を出す場合、SUMIFSでは対応が難しいですが、SUMPRODUCTならこう書けます。
=SUMPRODUCT((B2:B100="営業部") + (B2:B100="販売部"), C2:C100)
括弧で囲んだ条件がTRUE(=1)ならC列の値を加算するという仕組みです。 慣れるととても柔軟な関数です。
「FILTER」関数と組み合わせた応用例(Excel365以降)
Excel365やExcel2021以降では、「FILTER」関数が使えるようになり、条件に一致するデータを抽出する操作が非常に簡単になりました。
たとえば「営業部の売上データだけを抽出」して合計する場合、次のように記述できます。
=SUM(FILTER(C2:C100, B2:B100="営業部"))
FILTER関数は「一致する行のみ」を返すため、SUMと組み合わせることで集計も非常に直感的になります。
ただし、FILTERは「#CALC!」などのエラーが出やすいため、条件に一致するデータがない場合の対応もセットで学ぶと安心です。
「IF」と「ARRAYFORMULA」で条件付き計算を柔軟に
Googleスプレッドシートを使用している場合や、関数の応用力を高めたい人におすすめなのが、「IF」と「ARRAYFORMULA」の組み合わせです(Excelでも配列数式で応用可能)。
例えば、「営業部のみの売上金額、それ以外は0」といった条件付き合計は次のように記述できます。
=SUM(IF(B2:B100="営業部", C2:C100, 0))
通常はCtrl+Shift+Enterで配列数式として入力する必要がありましたが、最近のExcelバージョンでは自動配列対応になり、使いやすくなっています。
このような手法を知っておくと、「関数でできること」の幅が一気に広がります。
06. 関数を「使いこなす」コツと練習方法
実務を模した表でトレーニングしよう
関数は「読んで理解する」だけでは定着しません。 実際に手を動かして使ってみることが最短の上達法です。
たとえば、以下のような表を自分で作ってみましょう。
- 日付・担当者・部署・売上金額・商品名
このデータをもとに、「○○部の△△さんが4月に売った商品数」や「特定商品だけの売上合計」など、目的別に関数を当てはめていきます。
繰り返し練習すれば、関数の構造が自然と頭に入ってきます。
よくあるエラーとその直し方
関数を使っていて出会う「#VALUE!」「#NAME?」「#REF!」といったエラー。 これは「関数が悪い」のではなく、「範囲や条件の指定ミス」がほとんどです。
代表的な原因は以下のとおりです。
- 範囲のセル数が一致していない(SUMIFSやCOUNTIFSで特に多い)
- 条件が文字列なのに、ダブルクォーテーションで囲んでいない
- セル範囲の中に文字と数値が混在していて計算できない
関数の結果がおかしいときは、ひとつひとつ条件を分解してチェックしてみると原因が見えてきます。
「関数は怖くない」思考法のすすめ
関数は「パズル」や「レゴブロック」のようなもの。 最初は複雑に見えても、ルールと型さえ理解すれば、どんな関数でも応用が効くようになります。
ポイントは、「難しい式を丸暗記しない」「実務に合わせた問題から入る」こと。 使いながら「この場面で使えるな」と実感を得ると、一気に自信がつきます。
完璧を目指すのではなく、「使いながら覚える」スタンスで、あなたも今日から“関数を使いこなす人”の仲間入りができます。

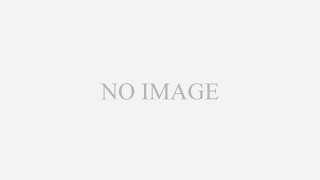
コメント